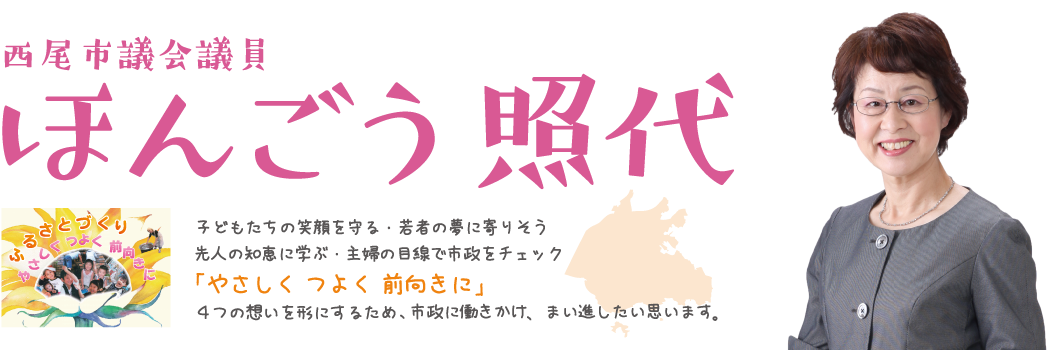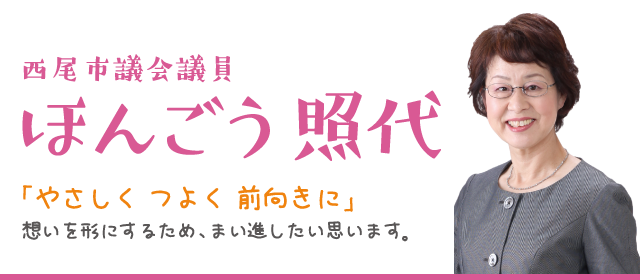5月7日(月) 今年の連休ほど何事につけ大荒れの連休はなかったのでは。 高速バスの事故に始まり、爆弾低気圧、大雨、登山者の遭難、 竜巻、そして原発の稼働停止・・・と続きました。 何かしら心の落ち着かない思いの一週間だったのは私だけでは ないと思います 昨日、私の住む地域では住民総出で「どぶ清掃」が行われました。 グレーチング蓋を取って泥を掻きだし、周りの草を取る、という 程のものですが、こういう機会にご近所と色々お話をするのも 楽しみの一つです デマンド型タクシーのこと、値上げの話が出ている区費のこと、 もっと実際に合った防災訓練のこと・・・皆さんの関心は様々です。 ついでだから、と家の裏側の…
2012/05/07